疲れやすい、やる気が出ない…それ、男性ホルモンの低下かも?
「最近なんとなく元気が出ない」「性欲が落ちた気がする」
そんなあなた、それは**男性ホルモン(テストステロン)**の低下が原因かもしれません。
男性ホルモンは筋肉・骨格・性機能など、男性らしさを支えるホルモン。
加齢やストレス、生活習慣の乱れで分泌量が減少すると、体と心にさまざまな変化が現れます。
この記事では、男性ホルモン低下のサイン、よくある質問、今日からできる対策法までを初心者向けにわかりやすく解説。
「もしかして…」と思った方に、今後の行動のヒントとなる内容をお届けします。
男性ホルモンの低下サイン【代表的な症状5つ】
男性ホルモンの低下には明確な兆候があります。以下に挙げる5つのサインは、特に40代以降の男性に多く見られます。
【1】疲れやすい・慢性的なだるさ
日中の眠気や朝の寝起きの悪さは、テストステロンの分泌量が減ることでエネルギー代謝が落ちている可能性があります。
【2】性欲の低下・勃起力の減退
テストステロンは性欲や性機能と密接に関係しています。パートナーとの関係に悩みが出てきたら、ホルモンの影響を疑ってみましょう。
【3】筋肉の衰え・体脂肪の増加
筋肉が落ちてお腹まわりに脂肪がつくのは、テストステロンの減少による筋肉合成力の低下が原因かもしれません。
【4】イライラしやすい・気分が沈む
精神面にも影響が及び、うつっぽくなったり情緒不安定になったりするケースも報告されています。
【5】集中力・記憶力の低下
仕事中に集中できない、物忘れが増えた…これもホルモンバランスの乱れによるものと考えられています。
よくある質問|男性ホルモンに関するQ&A
Q1. 男性ホルモンはいつから減少するの?
テストステロンは20代後半をピークに、年1%程度減少していくとされます。40代からはより自覚しやすい症状が現れやすくなります【出典:日本泌尿器科学会】。
Q2. 男性更年期との違いは?
「男性更年期障害(LOH症候群)」は、ホルモン低下による体調不良が顕著に現れた状態です。単なるホルモン低下よりも、日常生活への影響が大きくなります。
Q3. テストステロンは検査できる?
可能です。泌尿器科や男性専門クリニックで血液検査を受けることで、「遊離テストステロン」の値を調べることができます。
Q4. 男性ホルモンが少ないと不妊の原因になる?
はい。テストステロンは精子の質や精巣の機能に関わるため、低値だと不妊症のリスクが高まるとされています。
男性ホルモンを増やす5つの方法【生活習慣で実践可能】
以下の方法は、初心者でも手軽に始められる実践法です。
- 質の高い睡眠をとる
→ 毎日6〜8時間、規則正しい睡眠はホルモン分泌の基本です。 - 筋トレや有酸素運動を習慣にする
→ 特にスクワットやデッドリフトはテストステロンの分泌を促すとされます。 - 亜鉛やビタミンDを含む食事を意識する
→ 牡蠣・赤身肉・卵黄・納豆などをバランスよく摂取。 - ストレスを減らす生活環境を整える
→ 趣味の時間を作る・瞑想・自然に触れるなども効果的です。 - 過度な飲酒・喫煙を控える
→ アルコールやニコチンは男性ホルモンの生成を阻害すると言われています。
サプリ・漢方・ホルモン補充療法|男性ホルモン対策の選択肢
| 対策 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| サプリメント | 亜鉛、アルギニン、トンカットアリなどの成分 | 継続と相性がカギ。医師と相談するのが安心 |
| 漢方薬 | 八味地黄丸などが用いられる | 自然な改善が期待されるが、効果には個人差あり |
| TRT(ホルモン補充療法) | 医師が処方する注射・ジェル・貼付薬など | 副作用リスクあり。専門機関での管理が必要 |
厚生労働省のガイドラインでは、テストステロン補充療法は医師の判断のもと適切に行うことが重要とされています【出典:厚生労働省「LOH症候群診療の手引き」】。
まとめ|男性ホルモンの低下に気づいたらすぐできることから始めよう
- 男性ホルモンは年齢とともに自然に減少しますが、生活習慣の改善である程度の回復は見込めます。
- 体や心に異変を感じたら、「年のせい」と放置せず、医療機関でのチェックやセルフケアをスタートするのがおすすめです。
あなたのこれからの元気と自信のために、「ちょっと気になる」を放置せず、今日から行動してみませんか?
よくある質問(FAQ)
Q1. 男性ホルモンが減ると性格も変わるの?
→ 感情が不安定になることがありますが、適切な対策で改善も可能です。
Q2. 何を食べると男性ホルモンが増える?
→ 亜鉛・ビタミンD・良質なたんぱく質を含む食品がおすすめです。
Q3. サプリだけで効果が出る?
→ 基本は生活習慣の改善。サプリはあくまで補助として使いましょう。
Q4. テストステロン補充療法は安全?
→ 副作用のリスクもあるため、医師の診断・管理のもとで行う必要があります。
Q5. 何科を受診すればいい?
→ 泌尿器科または男性更年期外来のある病院が適しています。
参考文献・出典
- 厚生労働省「LOH症候群診療の手引き」
https://www.mhlw.go.jp/content/000969136.pdf - 日本泌尿器科学会「加齢男性性腺機能低下症候群」
https://www.urol.or.jp/lib/files/other/guideline/30_loh_syndrome.pdf
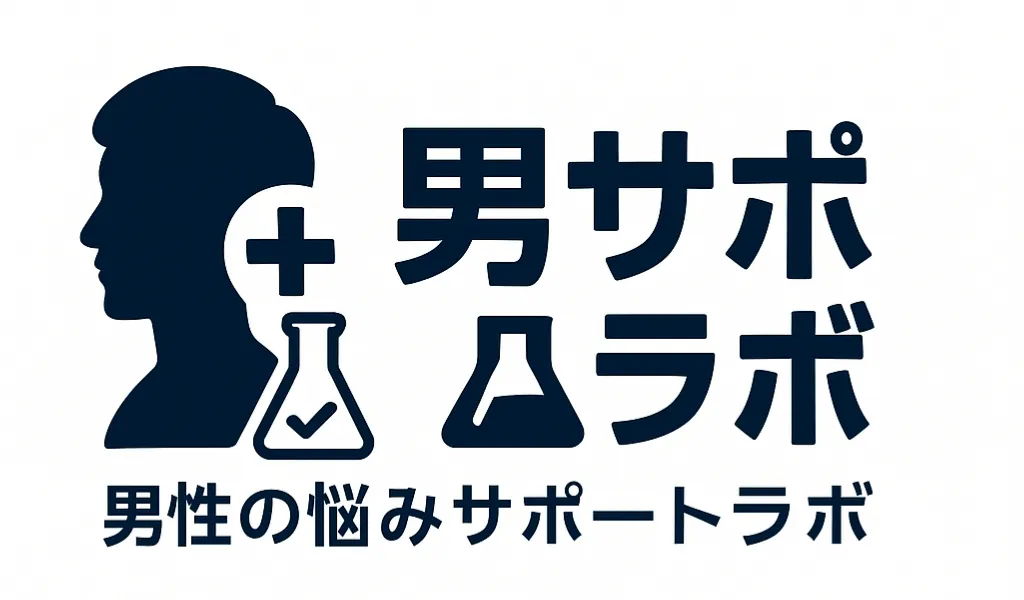



コメント